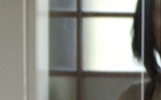出品・出演者紹介
35アーティスト・2レーベル・1グループ
(50音順)

出品・出演者紹介
35アーティスト・2レーベル・1グループ
(50音順)

World's End Satellite(大塚勇樹)ワールズ・エンド・サテライト(OHTSUKA Yuki)
プログラムE/F/G
1986年京都府生まれ。現在、大阪芸術大学大学院にて電子音響音楽の創作を中心に研究する傍ら、クラブ・ミュージックやエレクトロニカのトラック・メイキング、コンサートの録音/音響技術等の活動も展開。KAAF2010では[World's End Satellite]名義での初ライブを敢行。本名名義でのアクースモニウム演奏も行う。CCMC2009、2010入選。http://www.myspace.com/worldsendsatellite






















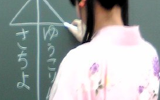




有馬 純寿 ARIMA Sumihisa
プログラムB
1965年生まれ。エレクトロニクスやコンピュータを用いた音響表現を中心に、現代音楽、即興演奏などジャンルを横断する活動を展開。自作のライヴ・パフォーマンスのほか、室内アンサンブルのメンバーやソリストとしてこれまでにケージ、ブーレーズ、フェラーリ、湯浅譲二、一柳慧など多くの作曲家の作品の音響技術や演奏を手がけ高い評価を得ている。ソロCDに「A Study in helix」などがある。現在、帝塚山学院大学准教授。
石上 和也 ISHIGAMI Kazuya
プログラムA/B/E/F/H
1972年大阪府高槻市生まれ。1990年大阪芸術大学音楽学科音楽工学コース入学。電子音楽や実験音楽を志村哲氏、コンピュータ音楽を上原和夫氏に学ぶ。1997年に仏INA-GRMでの夏期アトリエに参加。1999年神戸のアーティストグループ"ACTE KOBE"に参加して以降、欧米のアーティストとのライブを積極的に展開する。2007年中国・上海大学でのサウンド・ヴィデオ作品"Zen Matrix"初演や、2005年から08年にかけてドイツ国営放送から"2nd 49"、"Whisper of Sound God"などの委嘱を受ける等、幅広い活動を行う。大阪芸大、京都精華大学および同志社女子大学非常勤講師。ノイズ系の名義Daruinでも活動し、自主レーベルNEUS-318およびC.U.E records主宰。http://www.neus318.com
泉川 秀文 IZUKAWA Hidefumi
プログラムB/C/H
虚無僧尺八を志村禅保師に師事。京都・明暗対山流を中心に各派本曲を学び、特に地無し尺八による吹禅、音味・間の可能性を追究している。また今春、尺八古典本曲を研究した博士論文、現代音楽作品の作曲により博士号を取得。CCMC08作曲コンクールにて第1位ACSM116賞、FUTURA奨励賞を同時受賞。SIGMUS(情報処理学会)夏シンポ09にてベストプレゼンテーション賞を受賞。東洋音楽学会、情報処理学会、虚竹禅師奉讃会、虚無僧研究会会員。現在、大阪芸術大学、神戸山手短期大学講師。
生形 三郎 UBUKATA Saburo
[プログラムG]
作曲家/音楽家、1983年東京生まれ。独学での作曲活動を経て、昭和音楽大学にて作曲を秋田和久、矢内和三、由雄正恒、吉原太郎の各氏に学んだ後、東京藝術大学大学院(先端芸術表現科古川研究室)にて学際的な視点から電子音響を主体とした創作や研究を行う。大学在学中、国内外の電子音響音楽コンクール入賞をきっかけに、ACSM116主催夏期アトリエ・パリに参加しアクースマティック芸術の作曲と演奏を学ぶ。大学卒業以降は電子音響のパフォーマンスを世田谷美術館、仏国立シャイヨー劇場、アサヒアートスクエア、BankART NYKなど国内外各地で行い、独自のスピーカーシステムを用いた電子音響イベント「響彩陸離」を作曲家の柴山拓郎氏、堀川廉之氏らと共に主宰する。純粋な電子音響作品の他に、コンテンポラリーダンスとのコラボレーション等、電子音響を主体とした表現活動を行っている。
江村 瑶子 EMURA Yoko
[プログラムG]
2009年洗足学園音楽大学音楽音響デザインコース卒業、現在同大学大学院修士課程在籍中。電子音響音楽を制作していく中で空間音響や映像、身体表現と関わる機会を得て、複合的なメディア表現に興味をもつ。CCMC2008,2009,2010入選。CCMC2010にてACSM賞にノミネート、CCMC2009では電子音響音楽作品『Deplete of』がFUTURA賞を受賞し、フランスで開催されるFESTIVAL FUTURAに招待され、作品発表を行った。
及川 潤耶 OIKAWA Jyunya
[プログラムG]
1983年、仙台市生まれ。洗足学園音楽大学 音楽・音響デザインコースを経て、東京藝術大学 先端芸術表現科の修士課程に在籍。近年は、音楽とアートの領域にまたがる活動を展開しており、音響作品は"国際的な電子音楽の新しい傾向"と評され、ヨーロッパを中心とするフェスティバル等で紹介されている。2010年、斎藤高晴(映像作家)との作品"reminiscence"がTe Pito Recordsより発売。7月中旬にApple Store 銀座にてアーティストトークが予定されている他、秋には日本の美術館にて新作展示が予定されている。
大庭 恭平 OHBA Kyohei
プログラムE/G/H
2008年大阪芸術大学卒業。CCMC2010に入選。国際電子音響フェスティバルAudio Art Circus4年連続入選。芥川龍之介の後ろ姿を追い続け、気が付けば桜の花散る。さよならだけが人生だ。石川淳の饒舌体のごとくジャンルやかぎカッコつきの美術様式に染まらずに、しかし、芯の部分では染まりつつも、自覚的であるか?自覚的でないか? そんなことは自分でも分からない。今まさに耳障りな音こそが「ノイズ」なのでしょうが、現代では「ノイズ」はあまり耳にしませんね。「ノイズ」でさえも気持ちの良い時代なのですから。だから、プリファブ・スプラウトに熱き一票を、僕は入れる。
KAAG カーグ(関西アクースマティック・アート・グループ)
プログラムA/B/C/D/E/F/G/H
KAAG(カーグ/関西アクースマティック・アート・グループ)は、このフェスティバルの主催です。2009 年3月にアクースマティック・アートの表現活動を行う、 関西の5人の音楽家によって「とりあえず」結成されました。「とりあえず」とは、未だグループとしては、統一的な見解は無く、理念や主義そしてアクースマ ティックの可能性そのものへの疑問など、問題は山済みだからです。しかしながら「とりあえず」アクースマティック・アートの創造と普及、価値の向上を目 指して、我々はお互いに協力していこうね、と共感できている状況です。(次回、機会があれば、もっとキチンと主旨を表明しようと思います。たぶん。)ちなみにメンバーは石上和也、かつふじたまこ、檜垣智也、泉川秀文、竹下士敦、さらに大塚勇樹が加入。リーダーは不在です。権力争いはありますが、年功序列も成果主義 も今のところありません。「とりあえず」まったりと、しかし仲良しこよしグループではなく、獣のように澄んだ瞳で切磋琢磨しているような集団です。わかった?http://www.myspace.com/kansaiacousmatic
かつふじ たまこ KATSUFUJI Tamako
プログラムE
大阪生まれ。音作家。舞台音響家。90年代半ば頃から、詩や言葉を用いたテープ作品やシアターピースの制作を始める。2000年INA-GRM(パリ)にてミュージック・コンクレートを学ぶ。以降,国内外にて作品を発表。'04よりダンサーや美術家、映像作家らを巻き込み、音と他分野アートで空間を表現する『Full Space』シリーズを展開中。日常や非日常で聞こえたり聞こえなかったりした音に耳を澄ませ、拾い集め、紡いでゆく。そうして作り出された音作品は、日常のとなりのちょっとへんてこな世界を表現する。月猫音市場HP http://www.geocities.jp/hello_tsukineco/
小島 剛 KOJIMA Takashi
プログラムF
1995年頃よりラップトップを使った音楽活動を開始。以降、即興音楽を中心に国内外で演奏活動を行う。イメージや記憶が定着した様々なサンプリングソースの組み合わせから新しい音場を構築する作品を作りだす。これまでにミュージシャンだけでなく、ダンスやドローイングとのコラボレーションも多数。最近はロックバンド「シマクマガンホーズ」にバンジョー奏者として参加したり、バンジョーとラップトップと組み合わせた作品も作っている。
ピエール・シェフェール Pierre SCHEAFFER
プログラムC
1910年ナンシー生まれ。ミュジック・コンクレートの創始者。ブーレーズ、シュトックハウゼン、アンリ、フェラーリなどに大きな影響を与えた。2010年は生誕100年にあたり、世界中で彼の活動を振り返る催しが開催されている。1995年永眠。
志村 禅保 SIMURA Zenpo
プログラムB
大阪芸術大学音楽学科音楽工学専攻卒業。尺八を酒井竹翁、酒井松道に師事し、明暗対山派、根笹派錦風流、奥州系、九州系ほか各派の古典本曲を修得。また、研究活動として各地の伝承者から虚無僧尺八の吹奏技法を学び、学術博士号を取得。創作活動では、Cyber尺八プロジェクトを展開中。主著:『古管尺八の楽器学』出版芸術社。『事典 世界音楽の本』岩波書店(共著)。CD:浜松市楽器博物館コレクションシリーズ6「古管尺八1 - 音の表情」他。
スミス叙趣 Joshua SMITH
プログラムB
ニューヨーク出身。日本に住み11年。横山勝也系の岡田道明氏に尺八を師事。古典本曲と呼ばれる伝統的な禅独奏音楽を中心に勉強している。今春、大阪大学大学院を修了、博士号を取得。06年夏に四国八十八ヶ所を歩き遍路で巡り尺八を奉納演奏。世界尺八festival-S1GPにて青年の部第2位。09年當麻寺中之坊より「奏師」の号を授与される。08年独奏CD「白鳳音」を、09年には泉川秀文とのユニット『黒船』を結成し、尺八と電子音響音楽CD「黒船」を発表。虚無僧研究会終身会員、「石の会」会友。
Studio C+ スタジオ・セープリュス
プログラムG
北海道発信の電子音響、Electronica、Ambient、Experimental系レーベル。フランスGRMで電子音響を学び、Electronica・Ambientなど境界を超えた活動を展開するchiharu mkと、Kuniyuki Takahashi Bandなどでギタリストを務めClub Soundなども展開するマルチ・ミュージシャンのYoshihiro Tsukahara、シカゴの「Colorlist」などにも楽曲提供している3+、トランペット奏者西村伸雄とテルミニスト桑島はづきの即興ユニット「ちのはて」などが所属している。http://www.studio-cplus.net/
主なリリース・アルバム「piano prizm」「waterproof」chiharu mk/「Predawn-partly cloudy, but hopeful」 Yoshihiro Tuskahara/「Mother Leaf」3+/「Positive Feedback」ちのはて
炭鎌 悠 (仮) SUMIKAMA Haruka (kari)
プログラムE/G/H
大阪芸術大学音楽学科音楽制作コース卒業。大学在学中、アクースマティック・アートとやらに出会い、具体音や環境音を用いた電子音響作品を作り始める。
関 光穂 SEKI Mitsuho
プログラムE
大阪生まれ、B型、山羊座、社会人1年生。作曲を檜垣智也氏に師事。同志社女子大学音楽学科在学中に、ある日突然「コンピュータ音楽が学びたい!」と閃いて、ノックした扉の先にあったのは、アクースマティック・アートだった。いつしかその魅力に惹かれて、現在に至る。
竹下 士敦 TAKESHITA Hitonobu
プログラムA/C/D/G
ロック、アクースマティックを経て自分なりの音を探す音楽家。
田中 由希子 TANAKA Yukiko
プログラムE
1987年5月13日誕生。大阪府在住。本をよく読んでいるような気になっているが、実際はあまり読んでいない。文章、文字、詩のようなものを書き出していくのが好き。書き出していった中の詩を軸に展開していった映像作品「鉛のまぶた」がイメージフォーラム<ヤング・パースペクティブ2010>に選ばれ、東京で上映される予定。現在、次の作品の引き出しが出来るまでの隙き間を埋める「sound cushion」を制作中。
Te Pito Records テ・ピト・レコーズ
プログラムG
現代音楽とエレクトロニカの境界領域に響くインナー・アンビエンスを追求するレーベル、Te Pito Records(テ・ピト・レコーズ)。第一弾『Virtual Resonance』はBeams Records CD売り上げ週間ランキングNo1を記録、CDジャーナル誌上などで高い評価を受けた。第二弾『riminiscence』はオーディオビジュアルの新境地を切り開く音響映像詩。
中野 雄太 NAKANO Yuta
プログラムE
1982年10月20日大分市出身。福岡スクールオブミュージック専門学校音楽プロデュース科・総合音楽研究科卒業後、大阪芸術大学芸術学部音楽科へ編入し、同校卒業。現在は、国内外のアクースマティック音楽のコンクールへ参加する傍ら、サウンドプログラマーや、シンガーソングライター、声楽家など、"音楽家"として幅広い分野で活躍中。
中村 滋延 NAKAMURA Shigenobu
プログラムD
1950年大阪生まれ。1977年愛知県立芸術大学大学院修了。在学中の1974-76年ドイツ政府給費留学生(DAAD奨学生)。日本音楽コンクール作曲部門(71,73年),国際ガウデアムス作曲コンクール(75,76年),日本交響楽振興財団作曲賞(78年),日本音楽集団作曲賞(78年),「今日の音楽」作曲コンクール(83年),国立劇場舞台芸術作品賞(99年)などのコンクールの入選入賞多数。多様な創作活動の中の特徴は,視覚的要素を構成に取り入れた音楽作品の存在であり,コンピュータを積極的に応用することによって「音楽系メディアアート」というジャンルを確立,ICMC国際コンピュータ音楽会議や国際メディアアート賞(3回)で上演上映。『現代音楽×メディアアート』(九州大学出版会)などの著作も多い。ドイツZKM客員芸術家,日本音楽コンクール作曲部門審査員等を経て,現在,九州大学大学院教授(芸術工学研究院)
中村 秀紀 NAKAMURA Hidenori
プログラムE
岩手県生まれ。地元の工学部で有機化学を専攻するも、夢を追って音楽系の会社に入
社。サラリーマンとして音楽教育運営の道を歩むはずが、ふと電子楽器の開発に関わっ
た事をきっかけに、社会人になってから大阪芸大の門を叩き、電子音楽を檜垣智也氏
に学ぶ。卒業後は、かなり気長に作品の制作と発表をおこなっている。
趣味は、飲み会とブルーベリー栽培、サーバー運営など多方面にわたる。
名前 ゆ (仮) NAMAE Yu (kari)
プログラムE/H
電子音響音楽の制作や、鍵盤楽器の演奏などをしている。人生まだまだこれから。
成田 和子 NARITA Kazuko
プログラムE
アクースティックおよびアクースマティック作品の作曲家。スピーカーのオーケストラによるコンサートに多く携わる。同志社女子大学学芸学部音楽学科教授。
はたさちお HATA Sachio
プログラムE
写真家・映像作家・OHP投影。1995年頃より映像の制作、上映を始める。村上ゴンゾ,ASKATEMPLEなどの映像を担当。 OHP投影はフラワーマンなど。近年は写真制作に重点をおき、個展などを開く。 MASONNA, ACIDEATER, Runzelstirn & Gurgelstockなどの写真撮影なども担当。
韓 成南 HAN Sung Nam
プログラムE
記号論(言語・色・音・映像)を踏襲し、映像作品やアート作品を制作。Audio Visual作品、インスタレーション、アートパフォーマンス、ウェブアート等、活動は多岐に渡る。日本、韓国、オーストラリア各地で個展多数。Experimental Film and Video Festival in Seoul、Seoul New Media Festival Media Artist賞、Lausanne Underground Film and Music Festival、International Film Festival Detmold等国内外で上映・受賞多数。2009年12月にアジア圏唯一のaudio visual festivalを大阪で主催、オーガナイズした。Far East Audio Visual Socialization代表。<Web> http://jonart.net <FEAVS Web> http://feavs.org <FEAVS blog> http://blog.feavs.org <email> jonart.net@gmail.com
檜垣 智也 HIGAKI Tomonari
プログラムA/B/D/E
作曲・アクースマティック演奏。1974年山口県生まれ。愛知県立芸術大学大学院修了。フランス留学中にアクースマティックの作曲と演奏で注目を浴びる。2003年に日本へアクースモニウムを紹介し、国内でもコンサート活動を始める。数多くの音楽祭やコンサート・シリーズの設立・運営・企画にも携わっている。記録された音響とその空間表現をテーマに活動を展開。九州大学大学院、愛知県立芸術大学大学院、大阪芸術大学、同志社女子大学講師。現代音楽プロダクションMOTUS(パリ)と国際アクースマティック芸術祭FUTURAの常勤演奏家及び講師。
廣畑 祐子 HIROHATA Yuko
プログラムE
同志社女子大学コンピュータ音楽コース卒。コンピュータ音楽を落晃子氏、檜垣智也氏、石上和也氏に師事。音と映像と言葉を駆使して、独自の宇宙に浮遊していたい22歳。2010年4月からは、システムエンジニアの卵として殻を突き破るべく奮闘中。第2回学生デジタル作品コンテスト優秀賞及び特別審査員賞(中野伸二章)受賞。CCMC2009入選。第20回とよたビデオコンテスト奨励賞受賞。緑色が好き。
古舘 徹夫 FURUDATE Tetsuo
プログラムD
80年代より活動を続けるノイズ・ミュージシャン。2003年、ドレスデン「ドレスデン国際音楽祭」でポーの「アッシャー家の崩壊」をベースにした「ロデリック・アッシャー氏の聴覚」を上演、大賞受賞。2006年、ラジオ作品「求塚」がベルリン国際ラジオ芸術祭入賞。その後も欧州を中心にイスラエル、中国等でのコンサート活動を続ける。2008年、委嘱作品「ゴヤ」がドイチェンランド・ラジオにより放送。デュラス原作「ヒロシマ、わが恋人」をベルリン及び京都で上演。2009年、ケルン、ON - NEUE MUSIK Kölnにて狩野志保との共作ビデオ作品「WAVE / WIND」を上映。スウエーデン、イエテボリ・インターナショナル・フィルム・フェスティバル参加。新作ビデオ作品「ひとり みる つき」上映。
松本 祥代 MATSUMOTO Sachiyo
プログラムE
同志社女子大学コンピューター音楽コース卒。コンピュータ音楽を落晃子氏、檜垣智也氏、石上和也氏に師事。卒業制作ではサウンド・インスタレーションを制作。春からは化粧品メーカーに就職。CCMC2010にてFUTURA賞受賞。
村木 俊裕 MURAKI Toshihiro
プログラムE
現代美術家・デザイナー。1977年愛知県生まれ。2002年(~2003年)渡仏。2003年INA-GRM夏期アトリエ(パリ)にてミュージック・コンクレートを学ぶ。絵画から映像、インスタレーション等、表現領域は多岐に渡る。POST-SCOPE代表。
毛利 桂 MOURI Katsura
プログラムF
プリペアードレコードやシンバル、金属等をターンテーブル上で操るエクスペリメンタル・女性ターンテーブリスト。最近はコロンビアのポータブルプレーヤー2~3台を同時に操るなど常に独自のターンテーブル奏法を模索/追究し続ける。2009年にはericM、Martin Tetreault、Ignaz Schick らのターンテーブリスト達とヨーロッパツアーを行う。'98~2009年は実験ターンテーブルユニットBusratchとしても活動し、国内外の美術館やフェスに参加。又、京都でparrallax recordsの店長としてもいろいろ面白い実験音楽などを紹介する音楽のソムリエ?
森田 信一 MORITA Shinichi
プログラムE
電子音楽スタジオで作られていた電子音楽が個人のスタジオに移行し始めた時期に、江崎健次郎氏と出会い、電子音楽を学ぶ。音響デザイナー協会会員となり、その主催するコンサート“音展”で、1973年から電子音響作品の発表を始める。一方、1984年から1990年まで、作曲グループ“パッケージ21”で器楽作品を発表。2000年以降の創作の主体は電子音響音楽となっている。富山大学教授。
月見里 薫 YAMANASHI Kaoru
プログラムE
音や色。香りが好き。想いを言葉にするのが好き。自由な時間。自由な音楽。アクースマティックの作曲を檜垣智也氏に師事。遠い記憶をよく覚えている。なぜだかわからないけど天気。テレビの画面。言葉に出来なかった言の葉。匂い。予感。泣き虫だった自分。遠い記憶と今の記憶が今の自分を支えているようです。
RAKASU PROJECT. ラカス・プロジェクト
プログラムB
福山市在住。電子音響音楽から商業音楽制作まで、幅広い活動を行っている。電子音響音楽作品「砂利」第3回テクノアート大賞(東京国際美術館・東芝T-BRAIN CLUB主催)入賞(1993)。近年では、国内外のメディアアート関連フェスティバルにて、Max/MSP、Gainer、コンピュータ内蔵各種センサを活用したパフォーマンスや講演を多数行っている。同志社女子大学、京都精華大学、広島工業大学専門学校講師。
LISA リサ
プログラムE
1986年大阪生まれ。同志社女子大学音楽学科にて電子音楽と出逢う。音を軸に写真、映画など幅広く活動中。現在、早稲田大学芸術学校空間映像科第10期在学。

渡辺 愛 WATANABE Ai
プログラムE
作曲家・ピアニスト・アクースマティック演奏家。東京音楽大学大学院作曲修了。パリ国立地方音楽院在籍。受賞歴・公演歴多数。器楽・音響メディア・即興・アクースマティック(空間音響)・ダンス/映画音楽と活動は多岐に渡る。移動式音楽喫茶『秋福音』ほか即興ライブも精力的に展開。MOTUS夏期アトリエ、FUTURA、奨学金を得てACANTHES、IRCAM等参加。現在パリ在住。